
環境計量士を目指したいけど難しいそう。。。一体どのくらい勉強したら良いんだー!
こんな疑問にお応えします。
現在目指されている方やこれから目指そうかなと考えている方のご参考になれば幸いです。
ちなみに、この記事を書いている人は、水処理会社に10年以上勤めているエンジニアです。環境計量士は、ほぼ分析に関する知識がない入社2年目の時に独学で頑張って資格を取りました。
現在は水質分析業務や計量管理者の仕事もしているので全て経験に基づいて記載している内容です。
(読まれている環境計量士の勉強関連本のランキング記事はこちら)
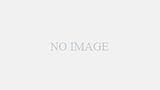
環境計量士の合格のためには300時間を確保しましょう
環境計量士を目指す同僚の方から、よく質問されることがあるのは資格取得に必要な勉強時間です。
勉強時間を確保してスケジュールを立てるのは、資格取得に非常に有効です。
いきなり300時間も?と思うかもしれませんが、環境計量士については試験範囲がかなり広いため沢山の勉強時間が必要になります。
ちなみに環境計量士の試験は非常に難しく、東大卒の人でも仕事が忙しく落ちたのを見たことがあります。なんでもそうだと思いますが、難易度の高い試験なので時間をかけて勉強する必要があります。
ちなみに2020年の合格率は濃度関係で15.4%です。(経産相HPより)
取得するとどんなメリットがあるの?についてはこちら⬇️

出来る限り効率的に勉強するために
※時間の使い方と、オススメの教材・テキストは後半に書いてますので、ここは読み飛ばしても構いません。
環境計量士を目指す方法は大きく分けて2つあると思います。
- スクールに通う
- 独学で勉強する
1.について、私が試験を受けたときは、環境計量士のスクールはなかったと思いますが、ネットで調べると少し出てくるようです。受かる確率を少しでも上げたい!という方は、お金を払ってスクールに通うのはアリだと思います。
スケジュール管理含めて、勉強方法についてはスクールで整理されていると思いますし、お金を払うので、受験に臨むモチベーションも維持しやすいのかなと思います。
2.について、スクールに通うのもいいけど、費用がかかるので、やっぱり独学で学習したい方もいると思います。
私の場合は、スクールがなかったのとお金がなかったので独学しか選択肢がありませんでした笑
おそらく、受験者の中でスクールに通われている方は周りとネットを見ている限り一部だと思います。
環境計量士の独学での勉強方法は?
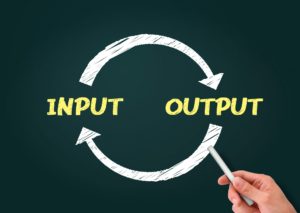
いきなりですが、勉強の仕方はアウトプット(過去問を解く)→インプット(テキスト・教科書で基礎・応用知識を得る)を繰り返すことが基本です。
- アウトプット:過去問を解く
- インプット :テキスト・教科書を読む
この両輪が大事です。
ちょっと横道にそれますが、こちらの本を読むとアウトプットの重要性が分かります。
アウトプット:一番重要なのは、はじめに過去問を解いて問題の中身と傾向を知ること
効率よく学習を進めるために、過去問から解くこと一番初めにやるのが効率時です。
こちら⬇️は2冊に分かれる分、解説のボリュームがあり深いところまで学べます。上記と比較すると良いです。
ちなみに、時間をそこまでかけて勉強しなくても良いのですが、計量関係法規・計量管理概論対策も必要なので、上記の過去問でも科目はカバーされていますが、この2冊の方が良いかもしれません。
※上記のものとこちらの2冊のどちらかがあれば過去問を勉強する上では十分です。
また少しマニアックになりますが、試験対策としても計量管理者としてもこちらの本は持っていると良いです。測定の信頼性の確保と評価などについては水質分析会社の方でしたら実際の業務でも考えておかなければなりません。
計量管理者の際にたまたま定期での立入検査があり、対応のために読みました。試験としても計量管理概論の対策にもなります。
基礎知識もないのに、過去問をいきなり解くのはナンセンスなのでは?
特に自分自身の知識が少ないと思っている方は尚更そう思うかもしれません。
ですが、”目的は資格の取得”です。
資格の取得には、必ずどんな問題が出るのか?を先に知ることで、どんな勉強をすればいいのか?ということが自ずと見えてきます。そのため、過去問を解き始めることをスタートにするのが資格取得までの一番の近道です。
最初の1週目は過去問を解き進めて理解するのが本当にしんどいですが、2周・3周と繰り返すと、徐々にモヤモヤしていた部分が少しずつ分かるようになってきます。
インプット:アウトプットで見えた試験の傾向から対策して基礎・応用知識を得る
過去問を解くことで見えてきた、こうしたら良いのでは?という勉強方法を実践していきましょう。
環境関係法規などに関する基礎知識
出題範囲は、環境関係法規からは、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等がでます。
化学は、基礎化学、量子化学、有機・無機化学、物理化学、、、とほんとに幅広いです。
環境関連法規については、自分の場合はその年に公害防止管理者を受けていたので、環境計量士の過去問だけでは足りないので勉強しました。
化学に関する基礎知識
化学については、試験範囲がほんとに幅広いので特にこれといったおすすめのものはありません。
大学の時に使っていたアトキンスの教科書で勉強していました。
あとは、基礎化学をもう一度勉強しようと思ったので、こちらのテキストを使っていました。
これが結構わかりやすかったので、ご参考まで載せておきます。
いずれにしろ、化学の基礎についてはこれだけでは足りないので参考までこちらも載せておきます。
大学レベルの教材が必要です。内容としては大学で初めて化学を学ぶ方向けぐらいのレベルです。
また自分の場合は有機化学が苦手だったので、有機化学の演習に特化した教科書を使いました。こちらは実際に試験勉強で使っていました。有機化学の出題は比較的多いので重点的にやった範囲の一つです。
化学分析概論及び濃度の計量
過去問を解いていくうちに、ガスクロの検出器の種類?この物質は何で測る?とかいろいろ扱った分析機器などが出てきますので、過去問の文章を読んでいるだけではイメージしきれないものあると思います。
そこでおすすめしたいのがこちらの参考書です。
分析の基礎的な理論や分析機器について、図解入りで非常に分かりやすい説明があります。また、計量管理概論に関連する、統計上処理や分析の評価などについての解説もあり、非常に参考になりました。
実務にも役に立ちます。
アウトプット→インプットを繰り返し学習することで、効率よく資格勉強が進むと思います。
最初の1-2ヶ月で過去問5年分を3回くらい繰り返し解いて、傾向を把握してからインプットに時間を費やしたほうがいいでしょう。
300時間の使い方は?
ざっくりのイメージですが、300hの勉強時間配分は以下の通りです。
- 過去問アウトプット:120-130h ←最低でも3回繰り返し解く
- 教材インプット:150h ←基礎からやる方は大学レベルの基礎化学の教材を1冊やり切る
- 関連法律暗記:20-30h ←試験1ヶ月前頃からで間に合うので頭に入れる
これからの勉強方法に参考になれば幸いです
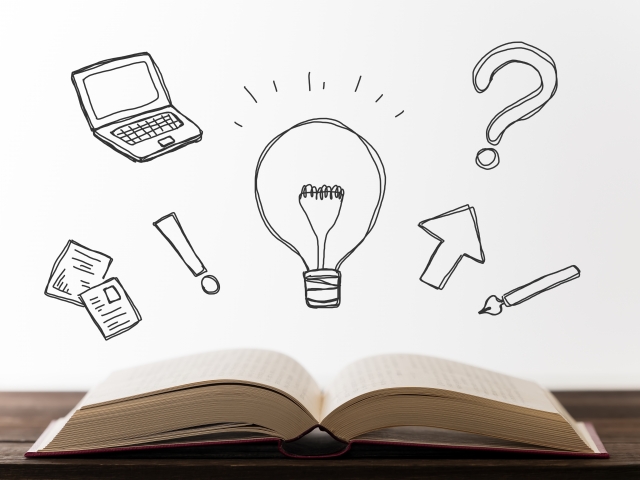


コメント